速読と記憶法の専門校
 当セミナーの速読法
当セミナーの速読法
当セミナーの速読法について、通常の読書と比べながらわかりやすくご説明します。
速読の”速さ”とは?
 まず、速読の”速さ”とはどの程度の速さなのかお話しましょう。
まず、速読の”速さ”とはどの程度の速さなのかお話しましょう。
ふつう私たちは、1分間で平均600字の文字を読めると言われています。普通の文庫本は1ページ平均600字で書かれていますから、単純にいうと「1ページを1分」で読んでいるのです。
もし速読法を身につけて1分間に1万字読めるようになると、1分間に16ページも読めることになります。これは「1ページを4秒」で読み、240ページの本1冊を15分で読める速さです。
通常の読書
ふつう私たちは「1ページを1分」で読んでいる、とご説明しました(速読の”速さ”とは?)。これをもっと詳しく見てみましょう。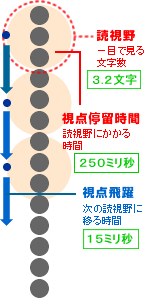
私たちは読書をしているとき、「ぱっと何文字か見て、また次の何文字かをぱっと見て、また次の何文字かをぱっとを見て・・・」という視点移動を繰り返しています。
国立国語研究所などの研究によると、一度にぱっと見ることのできる文字数はふつう約3.2文字といわれています。また、「ぱっと見ている瞬間」というのはどのくらいの時間なのかというと、約250ミリ秒、つまり4分の1秒です。ぱっと何文字か見た後、次の範囲に視点を移動する時間は約15ミリ秒です。ぱっと一度に見ることのできる範囲を「読視野」、ぱっと見ている瞬間を「視点停留時間」、視点の移動時間を「視点飛躍」といいます(左図)。
つまり私たちは読書をしているとき、「約3.2文字を250ミリ秒で見て、15ミリ秒で次の3.2文字に視点を移動している」のです。
速読の読書
速読の読書は、通常の読書とどこが違うのでしょうか?
速く読めるしくみ
通常の読書では「約3.2文字を250ミリ秒で見て、15ミリ秒で次の3.2文字に視点を移動している」とご説明しました(通常の読書)。まさにこの一連の流れの中に、速く読むポイントが隠れています。
まず、ぱっと一度に見ることのできる文字数3.2文字を増やします。次に、ぱっと見ている瞬間約250ミリ秒を短くします。さらに、次の範囲に視点を移動する時間約15ミリ秒を短くします。つまり、「ぱっと見る文字数」を増やし、「ぱっ」の時間を短くし、次の文字に移動する時間を短くする、これが当セミナーでお教えする速読法です。
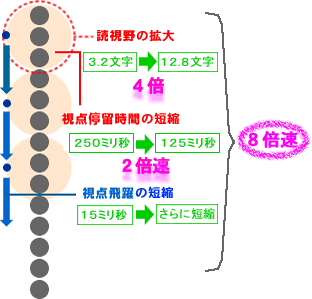
どのくらい速く読めるようになるのか
では、この速読法でどのくらい速く読めるようになるのでしょうか?個人差はありますが、トレーニング開始時に1分間400字程度だったのが、トレーニングの結果、1万字から多い人で10万字近くにもなっています(速読マスター実績をご覧ください)。とても速く感じるかもしれませんが、「できない、ありえない」世界ではありません。例えば「読視野の3.2文字を2倍の6.4文字に、視点停留時間の250ミリ秒を半分の125ミリ秒に」なるようトレーニングすれば、読書速度は以前の4倍になります。さらに読視野を2倍の12.8文字にできれば読書速度は以前の8倍、これは普通の文庫本1冊240ページを30分で読める速さです(右図)。
1行が30〜40字で組まれている場合、12.8文字は1行の約3分の1にあたります。そこで「ぱっと1行の3分の1を捉えられる」ことが速読マスターのひとつの目安になります。もちろん上達には個人差がありますが、当セミナーでは、速読力が入学時の5倍速になるまで責任を持って指導させていただいております(5倍速保証をご覧ください)。
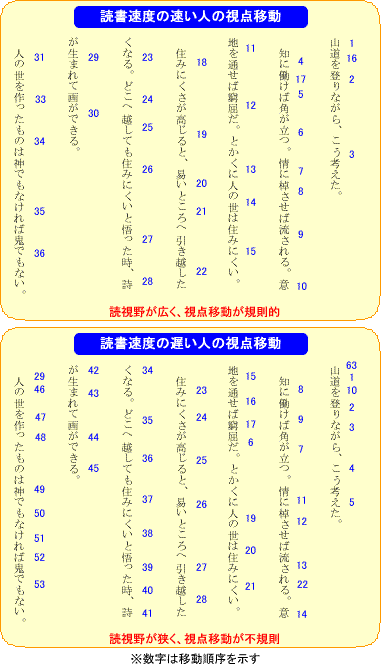
読むのを遅くする癖
読視野3.2文字を拡大し、視点停留時間250ミリ秒を短くし、視点飛躍時間15ミリ秒を短縮する、これが速読トレーニングの基本です。つまり、私たちの通常の読書方法のうち、速さに関する能力を伸ばすことが基本となります。しかし、これ以外に「読むのを遅くする癖」が読書を遅くしている場合があります。そこで、トレーニングではこの癖を取り除きます。読むのを遅くする癖には、視点飛躍・視点回帰、音読・内読などがあります。
●視点飛躍・視点回帰
読むのが遅い人は、文字を上から下へ、左から右へ規則正しく読んでいない場合があります。今見ている中心点から不必要な方向に視点が飛躍したり(視点飛躍)、すでに見た部分を再び見たり(視点回帰)するため、遅くなります(左図)。この癖を克服するには、「規則正しく上から下へ、左から右へ文字を読む」癖がつくようにトレーニングを繰り返します。
●音読・内読
音読では、読んでいる目と文章を音声を発している口の間に「ズレ」が生まれてしまいます。そのズレのために、口が音声を発し終わるのを待たないと、目だけで文字を先に読むことができなくなるため、読むのが遅くなってしまうのです。しかし、さらにやっかいなのは「音読している意識がない人」です。口元が動いている人ならすぐに気がつくことができますが、音読をしているのに声も出ず口も動かない人がいます。これを内読といいます。このやっかいな内読の癖を克服するには、先に読み急ぐトレーニングを繰り返します。
まとめると、速読とは、1)通常の読書方法のうち速さに関する能力を伸ばし(読視野拡大、視点停留時間と視点飛躍時間の短縮)、2)読むのを遅くする癖をなおして、速く読むことです。ですから、読書のできる方なら誰でもマスターできる速読法なのです。
よくある誤解
当セミナーでお教えする速読法は、読書科学に基づいています。しかし、世間では速読について様々な情報が氾濫しており、一部には「ものの数秒で1冊の本を読んでしまう」といった超能力まがいのパフォーマンスも紹介され、「どうも速読は疑わしい」「速読はまゆつばだ」という誤解が生まれることもたびたびです。速読そのものへの誤解は、速読をマスターする障害になりかねません。ここでは、「速読に関してよくある誤解」についてお話ししておきたいと思います。 速読は「特殊な能力」「超能力」ではない!
当セミナーの速読法は、速読の読書でご説明したとおり、通常の読書方法のうち速さに関する能力を伸ばすものです。ですから、一部の人だけがマスターできる「特殊能力」や人間の力ではできないような「超能力」ではありません。通常の読書ができる方なら誰でもマスターできる速読法です。
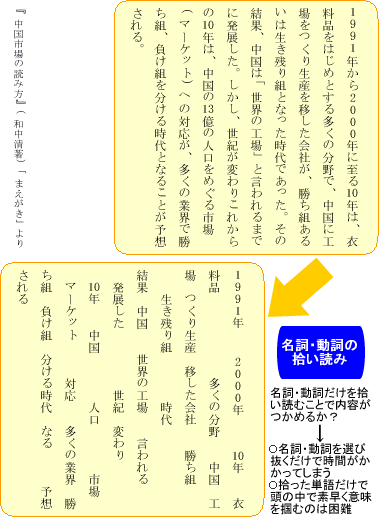
拾い読み、飛ばし読みは速読ではない!
拾い読み、飛ばし読みのやり方には、様々な方法があります。そのひとつに、文章の名詞と動詞だけを拾って読めば全体がわかる、という考え方があります。しかしこの方法では、拾った単語の機能(主語、述語等)をすばやく探らなければ文章を理解できません。単語の機能は全文を読んではじめてわかることではないでしょうか。つまりこのような拾い読み、飛ばし読みでは文章をほとんど理解できないか、拾った単語だけで頭の中で意味をつかもうとして理解が不確かになり、読むのが遅くなってしまうでしょう。
当セミナーの速読法は文章をすべて読む「全文読み」。「全文読みの速度を上げる」速読法です。
絵を見るように1ページを見るのは速読ではない!
1ページ分の文章をまるで絵を見るようにひと目で頭に入れると速く読める、という人もいます。しかし、私たちは絵を見るときでも、画面の構図や奥行きを知覚するために視点を動かしています。文章を読むときは、文頭から文末まで規則的に視点を移動させます。つまり、絵を見るときも、文章を読むときも、どちらも視点を動かすわけですが、絵と文章では視点の動かし方が違うのです。絵を見るようにひと目で文章1ページを見ても、文章を理解しながら速く読むことはできないのです。
速読では本の中身を鑑賞できないのではないか?
「速読では本の中味を味わったり、鑑賞することができない」、「速読とは、ただ文字を見たり、中味を暗記することだ」と考えている方もいるのではないでしょうか。この点は、速読をトレーニングするとき、注意が必要です。中味を理解しないやり方で「読むのが速くなった」という誤りが起きないよう、当セミナーのトレーニングでは、読み終えた後に本の内容を紙に書き出してもらいます(理解力トレーニング)。理解力を確認しながらマスターした速読では、理解力は通常の読書と同じです。「本の中味を理解する通常の読書」の速度を上げる、それが当セミナーの速読法です。